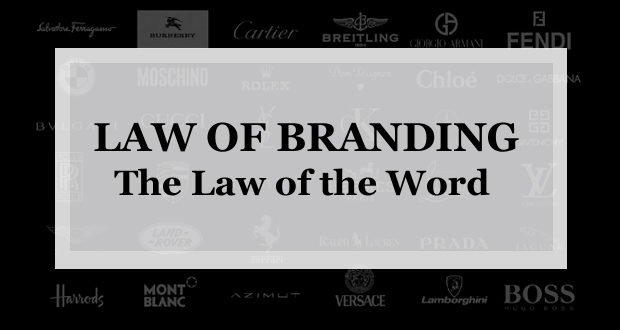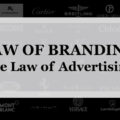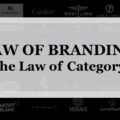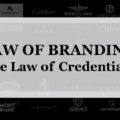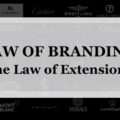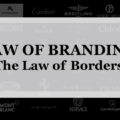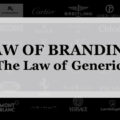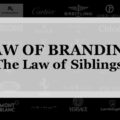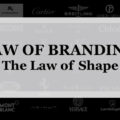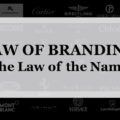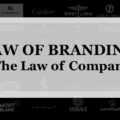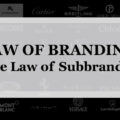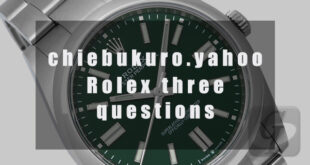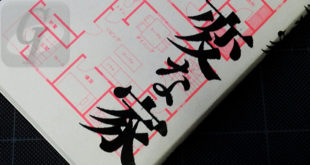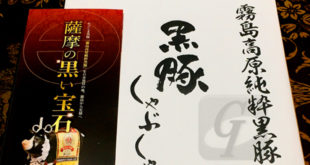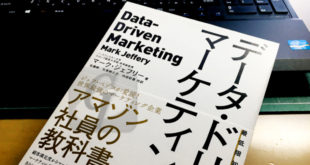ブランドが陥りやすい罠 それは自分の名前を他のカテゴリーにまで広げてしまうこと

今回の話は、多くのブランドが間違えやすい罠について多くのページを割いて説明している法則である。
前回【 ライン延長の法則:成功作を否定してラインの拡張を行う事はブランド力を著しく低下させる 】でも取り上げたが、あるカテゴリーで成功してしまうと、さらなる成長を求めて、自分の名前を他のカテゴリーにまで広げてしまうことをする事は、実は非常にリスキーなことである。
例としては、メルセデス・ベンツ を取り上げているが、まさに現在そのとおりの内容となっている。メルセデス・ベンツを購入を検討する場合、多くの人は「高級やプレステージ」などを頭に思い浮かべると思う。
このブランドからは、高価なドイツ製のブランドで、優れた技術と信頼性といったイメージを連想すると思う。
クルマに詳しい人であれば、最近までのメルセデス・ベンツは、そのイメージされるカテゴリーを広げ、安っぽいスポーツカー、低廉なセダンやRVなど、フルライン化に走った戦略で、ブランドの拡張に乗り出した。
メルセデス・ベンツブランドのブランド力があれば、どのカテゴリーでも一番売れる贅沢車となるはずだったが、蓋を開けてみると違っているのである。
このように、消費者のアタマの中に一つ言葉を所有した強力なカテゴリーを武器として他のカテゴリーを拡張するというのは、非常に困難であり、大半のブランドが誤った方向に向かってしまうのである。
引っ込みのつかないメルセデス・ベンツでも苦心しているのに、あなたが販売しているブランドはどうかともう一度問い直して欲しい。
ブランドづくりの第一歩は、焦点を絞り市場を創造すること
あなたのブランドを作りたいと考えるのであれば、シェアではなくどのカテゴリーで新しい市場を創造できるか、その創造した市場で、消費者のアマタの中に一つの言葉を所有できるかを考えて欲しい。
どのブランドの企業でも、当たり前に考えられていることであるが、この市場をつくるというのをもっと単純に考えて良いと思っている。
言葉遊びに聞こえてしまうが、他の誰も所有していない言葉を見込み客のアタマの中に一つの言葉を所有することに全力を傾けるということである。
例えばこのブログは、「ブランド・フォトライター」 の管理人磯守が書く、ブランドについてのブログである。稚拙な文章で、ライティングの勉強もしたことのない管理人だが、ライティングを通じて、ブランド・カテゴリーの研究を発表している。
この 「ブランド・フォトライター」 という言葉を検索しても出てこず、概念すら存在しないが、個人的には 「ブランド・フォトライター」 の立場でこのブログを執筆している。
「ブランド・フォトライター」 の概念は、自分の中では、当たり前の概念であり、このブログ自体が、商品であって、ビジュアルな実体なのである。
そしてこの 「ブランド・フォトライター」 のカテゴリーを創造すれば、多くの困っている人にとっての一番手のブランドとしての市場を創造できるのである。
つまりあなた自身が、誰も創造していないカテゴリーを創造すれば、極端な話ブランドは完成してしまうのである。
あとは、あなたが創造したカテゴリーを多くの見込み客や消費者のアタマの中に言葉を所有し、このカテゴリーでは、このブランド名であったり、第一人者であったりすれば良いのである。
ブランドづくりを振り返ってみても、成功しているのはカテゴリーを制したブランド
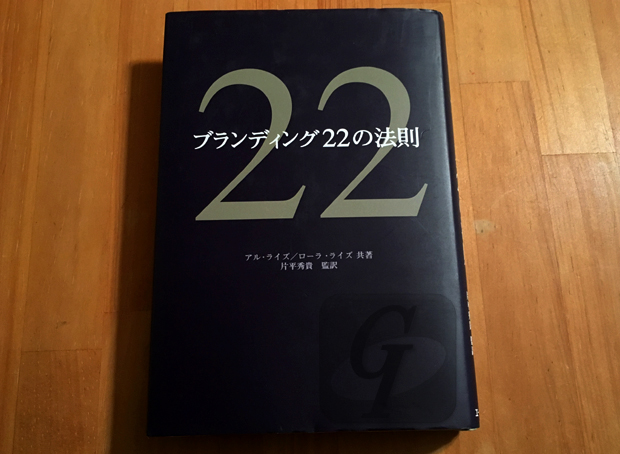
多くのブランドの歴史や現在主力で出しているモデルの研究をしているこのブログでも何度も説明しているが、共通しているのは、焦点を絞った商品づくりをしている点である。
つまりカテゴリー自体を拡張したブランドである。他のカテゴリーを拡張したブランドではないことを注意してもらいたい。
ここでも取り上げた、モンブラン が登場する前の高級万年筆市場はほとんど皆無であったし、ライカ が登場する前の小型高級カメラ市場においても、ライバルといえるブランドはほぼ皆無であった。
ボルボ は「安全」、メルセデス は「プレステージ・最善か無か」、BMWは「駆け抜ける喜び」、クリネックスは「ポケット・ティッシュ」、コカ・コーラは「コーラ」、ダウ・ケミカル は「サランラップ」など人々が、あなたのブランドを総称的に使う場合でも、ブランドネームがカテゴリー名を所有しても良いのである。
この市場の規模はどのくらいのサイズか。その中で私たちのブランドは、約 何パーセント獲得できるかという発想は捨てた方が良い。
あなたがブランドの成長を考えるなら、まとめるとこうなる。総称的になるまでカテゴリーを絞り、市場を創造して、消費者のアタマの中で、多くの特性と結びついているか、そしてそのカテゴリー自体をどこまで拡張していくかである。
参照:ブランディング22の法則
 Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"
Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"