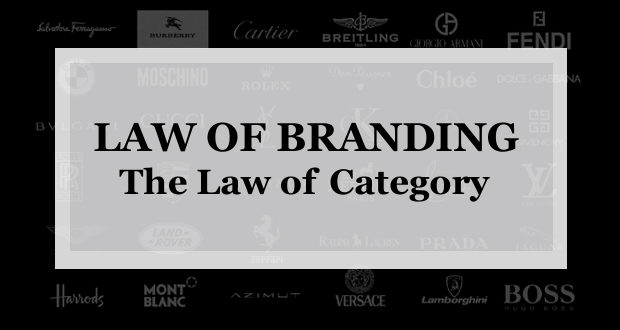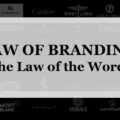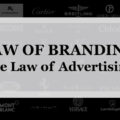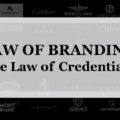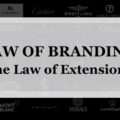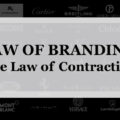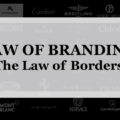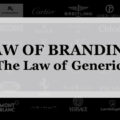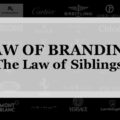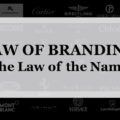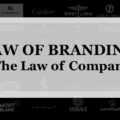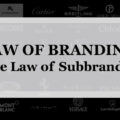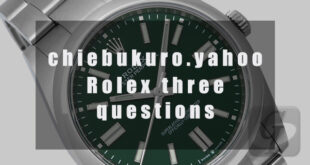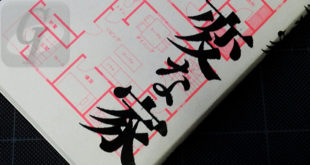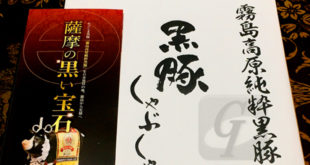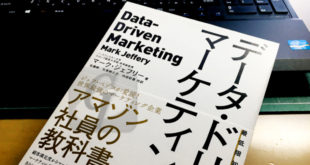既存市場のシェアを拡大することではなく新カテゴリーを創造することにある

あなたが、企業経営をし、ブランドを保有しているもしくは、個人ブランドを確立したい場合、新しいカテゴリーでリーダーとなることである。
企業の話では、本書で、米国飲食企業で、イーチーズ (eatzi’s) という企業を例に挙げている。その事業コンセプトは単純そのものである。高級レストランにあるカテゴリーの中から「テイクアウト」のみに焦点を絞り急成長を果たす。
その後、創業者は、会社を投資家グループに売却し運営にあたり、他店舗展開したが、上手く行かず、最初の店以外すべて閉鎖してしまう。創造したカテゴリーの拡張よりも、市場のシェアを獲得に動いた事が裏目に出たようである。
再び創業者が、商標と最初の店舗を買い戻し、事業の指揮を執り、原点に戻ることで再び成長軌道に乗せている。
この事例から分かるように、多くの顧客に共通して言えることは、あなたのブランドを気に留めているのは、ブランド自体ではなく、創造した新カテゴリーなのである。
ブランディングとは、既存市場のシェアを拡大することではなく、新カテゴリーを創造し、市場リーダーとして、その新カテゴリーを大きくしていくことなのである。
競合同士はシェアを取り合うのではなく、パイを大きく広げていくこと
多くの企業で新カテゴリーを創造した後、しのぎを削り、多くの業界で見られる傾向が、競合による存在をいかに取られているかである。
例えば、ゲーム機 市場では、プラットフォーム (機器本体) によるカテゴリーの競争が長く見られてきたが、スマートフォンの登場により、新カテゴリーを創造されてしまい、一気にカテゴリーの一角を奪われるという事例が見られた。
多くの競合は、スマートフォン登場前に、小さな通信機器にソフトを搭載して、プレイするという発想は、当時誰も想像できなかったわけである。
当時、携帯電話 の進化のスピードを考えれば、通信機器が、機械本体に成り代わるのではないかと、客側の立場を考えれば想像できると思われたが、ハード機企業は、通信機器との連携等深く考えず、自社本体の技術開発ばかりを優先して足下をすくわれてしまった。
この事例から言えることは、ハード機企業は、カテゴリーの創造の重要性を理解しながら、競合カテゴリーが、ゲーム機本体の脅威となる新カテゴリーを創造することが見えていなかったのである。
ゲーム機は、少数派の携帯機を除き、多くはテレビ画面もしくは、パソコン画面などを使い、本体とソフトを分け、それらを接続し、据え置いて、プレイするものだという価値観に引きずられた格好である。
新カテゴリーの拡張 (スマフォ等を取込む戦略) をたいして行われず、ハード機で、お互いのシェアの奪い合いをし、過ちを犯してしまう。顧客は、新カテゴリーを創造して、市場を急拡大している競合カテゴリー に、容易に乗り換えてしまった。
手軽にゲームを楽しみたい顧客の究極の欲求は、高額な本体など買わず、安価なプラットフォーム機一台でゲームも楽しみ、それ以外の機能も合わせて利用できる機器 という未来の新カテゴリーを探していたのである。
この事例は、カメラやパソコンの市場でも、同様の過ちを犯す事となるのは、賢明な皆さんも理解できると思う。
カテゴリーの創造をした後、何に取って変わられるかを常に注意しておくこと
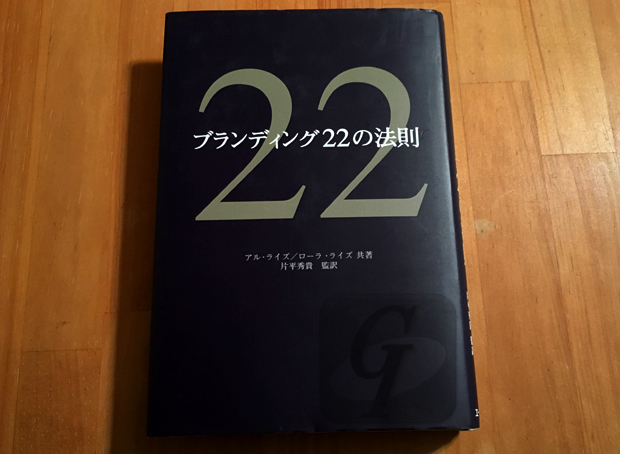
このように、新しいカテゴリーを創造した場合、競合ブランドの存在と戦うのではなく、競合カテゴリーと戦うことが重要である。
スマートフォンが登場したとき、同機能を搭載されてしまった競合企業は、その競合となるカテゴリー企業との戦い方をあまり考えていなかったように見えてしまう。
前回、【Polaroid SX-70は、A・ウォーホルを魅了しインスタグラムの流行に繋がる】 の件を取り上げたが、ポラロイドの経営戦略で最大の失策が、コダック をインスタントカメラ市場から締め出してしまった事である。
ポラロイドは、将来において市場を大きくしてくれる 同業他社の企業を排除してしまったのである。現在では、細々と市場を維持しながら、インスタグラム などの企業に寄ったサービスもしている。
あなたが、お勤めの企業もしくは、経営している企業の本当の戦うべき相手は、同業他社の競合企業ではなく、あなたの「利益源泉のルール」を変えてしまう企業なのである。
あなたが、サラリーマンやキャリアウーマンや個人事業主であれば、現在行っている仕事の内容が、何に取って変わられるかを考えれば良いのである。
それは、ロボットなのか ITシステム なのか、または他の第三者なのか、その時になってから考えるのでは遅く、今からでも、出来る限り対策を打っておく方が良い。
あなた自身(ブランド)を顧客に売り込むのではなく、自身が強みとし、築いたカテゴリー(専門にしている処理や解決能力)を売り込む事が重要なのである。
ブランディングを考えていくと、企業も個人も同じ結論に行き着くのである。
参照:ブランディング22の法則
 Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"
Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"