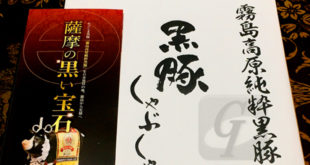財団からの美しき使者

AdSense
いまから数年前のある日、たしか秋ごろだっただろうか。私が経営する夢咲堂に勤めることになった 如月 綾 君が、少し痩せた長身の美しい女性と話をしている最中であった。
上手く接客している様子で、感心だなと思いながら、軽く女性に会釈をし、奥の事務室に向かうところで、綾君は私を呼び止め、応接スペースの椅子に座るように促されたのである。
「佐伯さん。ちょうどいい時に帰ってきてよかった」と綾君は、接客用のよく通る声で言った。
「査定依頼か何かかな。」
「そうなんですが、ちょっと変わっていて。」
「僕の専門分野であれば、話を聞くことは可能だけど、女性の依頼は、綾君の方が得意だと思うのだが。」
「今回のケースに関しては、佐伯さんの協力なしには、うまくいかないと思います。ここにいる佐伯さんは、あなたの依頼に必ず応えることができますし、私もお手伝いさせていただきます。」
少し痩せて、古風だが美しい女性は、綾君から勧められた椅子に座っていたが、両手を膝に置き、軽く会釈をし、うつむき気味で、丸く大きな茶色の瞳を素早く動かし、私を見て再び机の一点をみつめた。
「お茶をどうぞ。」と私は彼女にお茶を振る舞った。
綾君は、自分の事務専用の椅子に腰かけ、私は応接の来客用の椅子に軽く腰掛け、依頼人が話はじめるのを待った。
少し痩せた依頼人は、持っていたバッグの中から、一枚の書類を取り出し、机の上に置いた。綾君は、書類を手に取り目視を始めたが、私は、しばらく彼女を観察して、外見や容姿から、彼女の属性を知ろうとした。
年齢は、約三十歳前後。身長は、165 cm 前後ある細目のスタイル。髪はセミロングで、少しカールした黒髪。黒のコートに青のジャケット。白のブラウス、中央に長めのペンダントを身に着け、下は白系のパンツ、足元は黒のショートブーツを履きこなしている。
顔はよく見ると綺麗な二重瞼で、卵型の輪郭のせいか幼い感じにみえるが、どことなく影があり、そのせいか垢ぬけた外見をしていても、地味に見えてしまう。たしかあの女優にどことなく似ている。なんて言ったかな・・たしか木村なんとか。まあ、いいか。
彼女の表情は暗いが、それを除くと比較的裕福ながら正業に就いており、会計などを生業としている職業の人なのかと自分なりに推理の真似事をしてみたのである。私は一瞬目をやり、彼女の特徴を捉えるとそのままやり過ごす。

如月 綾は、パンフレットを一読すると、マネキンのような表情を一瞬で営業用の微笑みに変えながら優しく彼女に語り掛けた。
「経済的に大変な苦労をしてきたのは分かります。必死で勉強して学芸員の仕事に就き、今回あなたは仕事を失うかもしれない。ここに書かれた展示物になかに異常があった。それぐらいしか私には分かりませんけど。」
依頼人は、目を丸くし驚いた表情で、書類を受け取りながら、私に目を向けてきたのである。
「なぜそんなことがわかるのですか、如月さん?」と彼女に尋ねた。
「さあ、なぜなんでしょうね。」私が推理した内容とまったく違い、若干顔を引きつらせながら、綾君の方を見つめた。
「あなたのその服装や外見は大変オシャレですが、数年以上前の最新モデルで、経年によりバッグや靴に擦れや傷が見られ、いまは洋服や鞄を買えていないと推測できます。痩せてサイズは微妙に合っていないので、仕事で心労が重なり、必ずしも安定していないことがわかります。学芸員の話は、こめかみと鼻面のメガネの跡で研究系の職業というのが分かりますし、このパンフレットで、博物館で働いていることがわかってきます。博物館の人が古物を扱うここに来店するということは、今回の展示品に問題があったのは容易に想像できます。」
「すべてそのとおりです。しかし驚きました。佐伯さんの助手にこんなに優秀な方がおられるとは。」
「はは・・そうなんですよ。彼女は非常に優秀なスタッフでして、綾君そのパンフレットみせて。」
客の経済状況や素性を言い当てて、商売に響いたらどうすると心のなかで思いながら、たぶん私の顔は若干ひきつったままであろう。軽くパンフレットみて、以下の題名部分を読んだ。
~ 矢部銀次郎のコレクション展 ~
日本最大の時計会社グランドエイコー社を創業した「矢部銀次郎」氏による長年個人的に製作・収集してきた時価 百億円にものぼる ” 秘蔵のアンティークコレクション ” を市立博物館にて、限定展示致します。開催期間:11月1日~12月20日
「コレは凄い展示会ですね。日本でも有数の大富豪であり、グランドエイコー社の創業者である矢部銀次郎氏のコレクションは、長らく謎とされてきたと聞いています。」と高揚した気持ちと仕事への期待で、若干声がうわずってしまった。
「さっきお話した内容を最初から正確にお願いできますか。」と綾君は、マネキンのような美しい顔に戻り、機械音声のように、よく通る声で話を促した。私は、軽く腰掛け、自分のノートを広げメモを取る準備をして話をまった。
「さきほど、如月さんにお話しした通りなんですが、では佐伯さんがいらっしゃったので、最初からお話しさせていただきます。」と依頼人は少し顔を上げ、遠くをみつめながら言った。
「私は、鍋島 奈央子と申します。現在は、財団より出向し市立博物館で学芸員をしております。市立博物館と言いましても、矢部銀次郎氏の私財で博物館を建設し、その後 市に寄贈されたという経緯のある博物館でございます。展示企画についても、私たちが様々な企画をして、比較的うまく仕事をこなしておりました。つい先日亡くなられた前館長より仕事を託され、矢部銀次郎 氏の回顧展を開くため、長年収集した美術品や自身の製作した時計などの遺品整理と同時に、その記録とキュレーターの依頼があり、大量に収蔵された品物を再調査するように命ぜられました。」
「そのコレクションを調査する仕事の途中で何かがあったのですね?」と 如月 綾は尋ねた。
「はい。ところが、あるコレクションが偽物という人がいることを知らされました。」
「それは誰ですか?」と私は彼女に尋ねた。
「清水官兵衛 です。」
「誰です?」と少し驚いた表情で珍しく綾君は、私に尋ねてきた。
「清水官兵衛 は、天才的な時計修理技師だよ。現在は、三代目の清水官兵衛のお孫さんが跡を継ぎ、その技術は、代々受け継がれていて、日本で一二を争うほどの天才職人一家だよ。」
「その清水官兵衛さんに、コレクションであるアンティークモデルのオーバーホールに出して、すべて可動できるようにお願いをしたところ、ある懐中時計が本物ではないと主張し出したのです。」
「なぜそれが偽物ということがわかったのでしょうか?」綾君は丁寧に尋ねた。
「はっきりとした理由は教えてくれませんが、とにかくこれは、矢部銀次郎が製作した懐中時計ではないとの一点張りでした。」
「清水氏には、実際お会いしたことはないのですが、どんな方ですか?」と私は尋ねた。
「大変風変りな方だったようで、ご高齢の白髪がとても似合う感じの良い方です。大きな特徴としては、すごく太い眉とあごひげをお持ちで、眉もひげも真っ白で、まるで昔話で出てくる仙人のような方と思ったぐらいです。」
「で、その懐中時計はいまどちらにあるのですか?」私は尋ねた。
彼女はバッグから、小さな化粧箱を取り出した。紫のスエード調の外装に、施錠面に金色の小さなパドロック付きの上品な箱である。鍵を開けると中には、金製の懐中時計が収められていた。

AdSense
「矢部銀次郎のコレクションの中に、時価 五億円 相当のグランドエイコー・インヘリット N 型がございます。ご覧ください。これでございます。外装は、調べたところ、18金ということが分かりました。その装飾は、蓋や裏蓋までびっしりと植物文様が施され、内部の機械は複雑な技術を用いたトゥールビヨンが使われております。」
私と綾君は、驚きのあまり開いた口が塞がらず、しばらくその美しい懐中時計に目を奪われた。
「すごく疑問なのですが、なぜそのような高価な代物を持ってこれたのですが?」
私は驚きながら、なぜ彼女が持ち出せたのか疑問だった。
「持ってくるもなにも、この懐中時計がこの世に存在するということを知っているのは、清水さんのご家族、矢部家の一部の人間、前館長と私、それとあなた方二人だけです。私が持っていても、世間は誰も知らないわけですし、持ってくるのは調査中の資料ですので簡単です。インヘリット N 型は、グランドエイコー社の東京工場で、長期間保管されていましたが、戦時中の空襲で工場ごと焼けてしまい、それ以来、行方不明という話ですので。」
「で、私たちにどうしろと言うのですか?」
如月 綾は神妙な面持ちで尋ねた。
「この懐中時計を公に発表するために、インヘリット N 型の真贋をお願いしたいと思いましてお持ちいたしました。」
「なかなか難しい案件ですね。真贋はもっとも困難な仕事のひとつですし、もしかすると、永久に分からないかもしれないのですよ。」
リスクの高さを感じ、私は彼女に対し、予防線を張って答えた。
「分からなくても構いません。知っている方はわずかですし、はっきりしなければ、文字通りに再びお蔵入りとすればいいのですから。逆に知りたいのは、清水さんたちがなぜ偽物と主張するのか、古い時計にお詳しい夢咲堂さんなら真実がわかると思いまして。」
「わかりました。お引き受けいたしましょう。最後に質問ですが、なぜ私の店を選んだのですか?」
「佐伯さんのお父様で、佐伯 一郎さんの話を聞いたからです。清水さんがそれは楽し気に生前の一郎さんとの思い出を語って聞かせてくれましたので。」
「もう一点、コレクション展が始まるまで、一か月程度といったところですが、いつまでに真贋結果をお出しすればよろしいでしょうか。」と綾君が尋ねた。
「このコレクション展は、とうの昔に終わっております。それも四十年前の話です。」
私たちは、顔を見合いながら、同時に彼女をみつめたのである。
2 に続く
※掲載している小説はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
※掲載している小説の著作権は作者にあります。
※作者以外による小説の引用を超える無断転載は禁止です。行った場合、著作権法違反となります。
※Reference images in this article are Pixabay.
 Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"
Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"