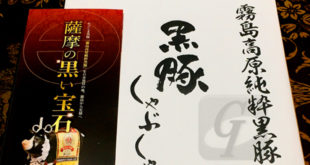間宮翔子の休日

AdSense
あれ以来、何度も考える日々が続いた。例の懐中時計の件について、最善と思っていた和解案を鍋島奈央子に軽く一蹴されてしまい、実のところ依頼を受けるべきではなかったと今更ながらに後悔していた。
- 瀬をはやみ 岩にせかるる 瀧川の われても末に 逢はむとぞ思ふ -
矢部財団から、いや、鍋島奈央子から借りているこの懐中時計。化粧箱の裏蓋を開きっぱなしにして、木簡の和歌を私は眺めていた。この和歌を調べてみたところ、崇徳院が詠んだ和歌で、その命により、1150年に編纂させた「久安百首」に載せられた一首であり、現代の言葉で訳すと、川の瀬の流れは速く、岩にせき止められた急流が、二つに分かれ、また一つになるように、今は愛しい人と別れても、いつか必ず再会し結ばれると信じている。といった意味である。
「ねえ。これ観てなんか意味あるの?」
私は、綾君にある落語の動画を観ておくように言われていた。今は、目の前に懐中時計を置き、自分の事務机の上にあるパソコンで、崇徳院 (落語) という、古典落語の演目の一つを鑑賞しているところだった。
「その演目面白いでしょう。フフッ…」
綾君は、仕事をしながらも、よく通るアナウンサーみたいな声とその美しい笑顔でこちらに問いかけた。さすが元・ソロアイドル…その営業スマイルが逆に怖いのであるが…なんだろう。綾君は、最近大変に機嫌が良く、何かしらの胸のつかえが取れたような、晴れやかな態度で仕事をしていた。少し前までの、マネキンのような表情で、眉間にシワを寄せていた時と違い、アイドルらしい軽やかさを私は感じるである。この場合、大抵決定的な「何か」が分かったのであろう。
「もったいぶらずに教えてくれよ。今日もなんでそんなに可愛いのかな?」
私は、半分冗談めかして綾君に問いかけた。私なりの称賛と敬意を込めた意味もあるのだが、綾君の返答はやはり手厳しいものである。
「そんなのだから、女心もわからない ” 薄ら禿のでくの坊 ” と鍋島さんに言われるのですよ。」
「お…おい。よくそんな汚い言葉をサラッと言えるな。」
たぶん綾君はハード寄りの超 S だ。これは間違いないのだが、その美貌から淡々と罵る言葉を発するがゆえに、一瞬分からないときがあり、分かってもその美貌ゆえ、大抵の男は許してしまうであろう。綾君は淡々と話しを続けた。
「簡単ですよ。この件は、どこにでもよくある男女間の縺れだと思います。考えてみてください。この懐中時計を清水氏は偽物と言った。これを本物と仮定すると、本物を偽物と言ったことになる。作った本人がそう言っているという事は?」
私は、少し椅子に持たれ掛けながら、天を仰ぎ、右側に目線を移した。

「本物は、自分が持っていると確信していて、その瞬間、偽物を作られたと思い込む。」
「そうです。清水氏の立場に立って考えていくと、ようやく真相の半分が分かってきました。清水氏は、本物を持っていたと思っていたが、実は自分が贋作と認識していた懐中時計をずっと持ち続けていたことに、約 50 年以上気づかなかったんです。」
「そんなことって考えられるのか?50年も気づかないなんて。」
「あれは、自分の愛する人に密かに贈ったプレゼントだったからです。ホラ。この和歌の意味するところは分かったと思いますが、ある若い男が恋焦がれ密かに愛する女性と再び出会い、一生愛を育みたいと望むその相手とは?」
「なるほど。清水氏の奥さんか。」
「そうです。清水官兵衛・三代目、通称:中井貴一さんの祖母にあたる人です。」
「その言い回し…もうちょっと飽きてきているだろう…。」
「ただ、決定的な証拠となる最後のピースがまだ解けていないので、今のところ推測の段階ですが、もう少し情報を集めないと分かりませんね。」
綾君は、鑑定した二つの懐中時計の資料と写真をパソコン上で見比べており、ビジュアル分析の最中であった。綾君は、事あるごとに現場で撮影を行い、そのビジュアルの関連性から大胆な推理を立てることが得意である。今回も、矢部記念博物館や清水時計修理事務所で現場撮影を行い、かなりの枚数にのぼる。それらを丁寧に調べている。
「佐伯さん。ひとつ教えてほしいのですが、先日調べた中で、清水氏の祖母の名前って知っています?」
私は、続きが気になっていた落語を再び観ており、いきなりの質問で面を食らってしまったが、落語を聞きながらも、左側においているファイルを開き、資料に目を通し綾君に伝えた。
「ああ、たしかまとめた資料のなかにあったと思うが…あったこれだ。えっと、さやという女性だ。」
綾君のいつものようにマネキンのような横顔を見せていたが、右側の口角が一瞬上がり、確信を得た表情に変わったところを私は見逃さなかった。
「なにかわかったのか?」
私は、綾君の座っている机の右側に行き、パソコンに写し出された写真を観ながら綾君をチラッとみた。
「ええ。たぶん間違いはないとおもいます。それより佐伯さん。調べてほしい情報を持って、午後にアポイントを入れていたあの人が到着する時間ではないですか?」
私は、壁に掛かっているお気に入りの時計を見ながら、あと数分で約束の時間ということが分かり、慌てて準備をはじめた。
「あと、奥の資料室で、午後からこの懐中時計を最後にもう一度調べたいので、店頭を少し空けてもいいですか?」
客人の来訪の準備のため、散らかしていた資料を片付けながら、左手で化粧箱に入った懐中時計を差し出し、綾君に渡して私は答えた。
「ああ。構わないよ。私は、彼女と調査報告の内容を聞くためにここにいるから心配はいらない。」

時間は、13:30分を少し過ぎたぐらいだろうか。店の玄関ドアが静かに開き、そこにスラっとした黒髪の女性が立っていた。その女性は、身長が非常に高いのが特徴的で、約 170 cm 前後あるだろうか。黒系の高いヒールを履き、黒のパンツ、同色のジャケット、同色のトートバッグを持ち、黒髪は腰辺りまでありかなり長い。また、端正な顔立ちで、目元が印象的なエキゾチックな女性で、若いのだが、どことなく若さよりも、落ち着きが感じられる。街で歩いていても、スカウトされるぐらい美しく、職業がモデルと言っても、誰もが信用するであろう。
「間宮探偵事務所から来ました間宮翔子です。」
間宮翔子と名乗るその女性は、玄関前で素早く名乗り、ゆっくりと私の方に近づき、軽く会釈をした。
「すっかり大きくなったね。高校の時以来かな。お父さんは元気にしている?」
間宮翔子は、屈託のない笑顔を私に見せた。
「ええ。お久しぶりです。佐伯さんも元気そうで。」
私は、応接用の椅子を引き、その椅子に座るようにすすめ、間宮は静かに席に着いた。
「私は、君のお父さんに依頼をしたのだが、まさか君からメールの返信が来るとは思ってもみなかった。お父さんの跡を継いだのかい?」
私は、片山伊右衛門商店の高級抹茶を入れて、間宮翔子をもてなした。
「いえ。父の手伝いをしているだけです。まだ大学に通っていますし、今は休みを取っていて、休学中にアルバイトをしています。」
私は、事務用の机から細長い茶封筒を取り出し、今回の依頼した報酬の入った封筒を間宮の手元に置いた。手に取りながら間宮は、カバンの中に素早く入れ、同時にカバンからクリアーファイルに入った書類を取り出し、タイトルに ” 鍋島奈央子における素性調査報告書 ” と書かれた書類をクリアーファイルから抜き、私の前に差し出した。私は、調査報告書を丁寧に熟読し、調査報告の疑問点を聞くことにした。
「彼女の人生をざっとみたところ、特に変わったところがないように見えるな。調べてみた印象で変わったところはなかったかな?」
間宮は、両手で茶器を取り、ゆっくりと抹茶を一口飲み、喉を潤したあと、質問に答えた。
「一見、どこにでもいる平凡な女性に見えますが、鍋島奈央子という女性の人生は、異常なことばかり起こっているという事が調査してわかってきました。いちばん異常なのは、彼女の周りで死んでいる人の多さです。」

AdSense
もう一度、調査報告書の最初のページを読みながら、次のページをめくろうとしていたが、思わず手を止めて間宮の方に目線だけをやり、そのままの姿勢で話を継いだ。
「なんだって。」
間宮は、どんな話し方をすれば私が食いつくのか、そのポイントを熟知していることが憎らしいが、小悪魔のような微笑みを浮かべ、私の方に顔を近づけ、さらに話を続ける。
「だって、どう考えても異常ですよ。彼女の中学・高校の親友は、みんな変死していますし、看護学校時代にも、友人が事故で亡くなったり、看護師になっても、病院内で死亡事故があったり、そのあと美術史を学ぶため、大学に入っていた時には、友人や恋人も、みんな奇怪な死を遂げています。今は、記念博物館で学芸員をしていますが、少し前に前館長が、死因がはっきりとしない心臓発作で突然死んでいます。最後に彼女の母親も少し前に自殺しており、彼女の周りには常に死人が出ていますが、すべて、自殺や事故、病気扱いにされています。彼女は何かしらの関わりがあったと私は見ていますが、決定的な証拠はありません。でも…私にはわかるの。」
間宮翔子を幼少の頃より知っているが、その鋭い観察眼は成長するたびに実感する。彼女のミステリアスで、独特な雰囲気に包まれるのであるが、それにも増して、二十歳を過ぎてから、そのミステリアスさに磨きが掛かり、同性すら惑わす色気が合わさり、いまからこれだと末恐ろしいなと思うほどである。少し前に、雑誌でなにかで見たのだが、フランスのある高級ブランドで、若くして日本人モデルを務めたあの娘にイメージが似ているが、くやしいが名前は忘れてしまった。
「佐伯さん。それからここ見てください。彼女の戸籍を調べていくと、母親しか記載されておらず、父親は誰か分からないですよね。ただ、彼女の母親を調べていくと、面白い事実が分かってきました。奈央子の母親がどこで仕事をしていたと思いますか。」
私は思いをめぐらし、丁寧に答えた。
「矢部時計製作所だろ。」
「あたり。 さらに考えてください。どの人の配下で仕事をしていたと思います?」
間宮は、身を乗り出し、さらに顔を近づけ、吸い込まれるような瞳で、私を見つめながら問いつづけた。ここまでくれば、私でも察しはつくのである。
「次男の順次郎の部下だった。その彼と何かあった…。」
間宮は、美しい姿勢に座りなおし、丁寧な所作で茶器に手を伸ばすと、抹茶を綺麗に飲み干し、膝に手を添え丁寧に会釈をして、私にこう切り返した。
「彼女は、間違いなく矢部家の末裔です。今度の件で、彼女は何かを策しています。これでもう綾さんから、女心もわからない ” 薄ら禿のでくの坊 ”と言われなくても済みますよ。」
私は一瞬ドキッとして、目を丸くしているのが自分でもわかるぐらい驚きの表情で、間宮を見つめつぶやきが自然ともれた。
「な…また唇を読んだのか。」
間宮の読唇術は、持ち前の視力と文脈を読み取るセンスで、遠隔からでもたちどころに内容を読み取ってしまう。私がみたところ、間宮には生まれつき不思議な才能を持ち、それを最大限に活かした ” 方略 ” を幼少の頃より心得ているようにみえる。
「じゃあね。佐伯さん、また今度ね。」
間宮は、静かに立ち上がり、背を向け歩き出したかと思うと、軽く立ち止まり、振り向きざまに、左腕を軽く上げ、手の指を動かしお別れの合図を送ったかと思うと、最後にミステリアスな笑顔を残し、足早に出ていった。
解決編 に続く
※掲載している小説はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
※掲載している小説の著作権は作者にあります。
※作者以外による小説の引用を超える無断転載は禁止です。行った場合、著作権法違反となります。
※Reference images in this article are Pixabay.
 Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"
Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"