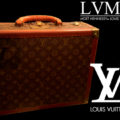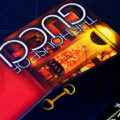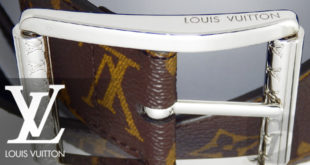LVMHの強み:ライセンスを切り自前主義のブランド構築

ブランドを保有し運営して経営する事なった場合、ライセンスは魔法であり、劇薬か麻薬のようなものである。ブランド価値があり、高価格で維持できるから、ライセンスが成り立つ。
ライセンスに手を染めるという事は、サインひとつで、後は相手が生産・流通・販売までを請負、寝ていてもロイヤリティーが入る仕組みである。
一度始めてしまえばなかなか止める事が出来ず、なかなかやっかいである。買収する側として、買収した企業がそれを収益の柱にしていれば尚更である。
高価で販売していたバッグに、様々な安価な製品に同じブランドロゴが付いた場合、ブランド価値は急落していく。なぜなら誰でも手に入れる事ができるからだ。
権力とお金を持った選ばれた人間が、保有を許されるのが 「本来の高級ブランド」 と考えるのであれば、安価なブランドにブランド価値は存在しないのに等しい。
このライセンスという禁断の麻薬のような手法を我慢するのは難しく、仮にライセンスに手を染め、それを止めて自前主義に引き戻す場合、生産・流通・販売のすべてを揃えるには資金も時間も人材も揃える必要がある。
仮に自前で用意できたとしても、成長著しいブランドが、ライセンスを使わずに、世界の市場を素早く展開できないだろう。
個人ブランドとしてラグジュアリー化に成功したブランドが、成長の壁にぶつかった時の手詰まり感を感じた場合、資金と販売のための流通・経営を維持する組織力がある LVMH のようなコングロマリットの傘下に治まれば、長期的にブランドの成長維持が可能になるのである。
ライセンスで失敗した ディオール、ライセンスをしない ヴィトン

ルイ・ヴィトンは、これまでライセンス生産はしてこなかった。それに比べ、かつてのクリスチャン・ディオールは、大半がライセンスだけで成り立つブランドであった。
ディオールのライセンス製品の品質は非常に低下、広げすぎたライセンス商品が市場に溢れ、流通のコントロールはほぼ不可能な状態に陥っていた。
ディオールのブランド価値は非常に低下し、もはや高級ブランドとはいえない状態である。現在の日本でもディオールの二次市場の価値はほぼないと言ってもよく、取引されても高額に取引されることは少ない。
それは過去のライセンス戦略が場当たり的で、自身で価値を失墜された原因であり、いまだに二次市場での価値はあまり高くない。その一方でルイ・ヴィトンは、再生する前に比べ、二次市場でも高い価値を維持し続けている。
アウトレットやライセンスがないというのは、新品市場とその中古しか存在しない限りは、高い価格を維持する事ができるであろう。それだけライセンスは諸刃の剣なのである。
ブランドを高価格で維持する秘訣はライセンスをせず自前で流通体系を持つこと
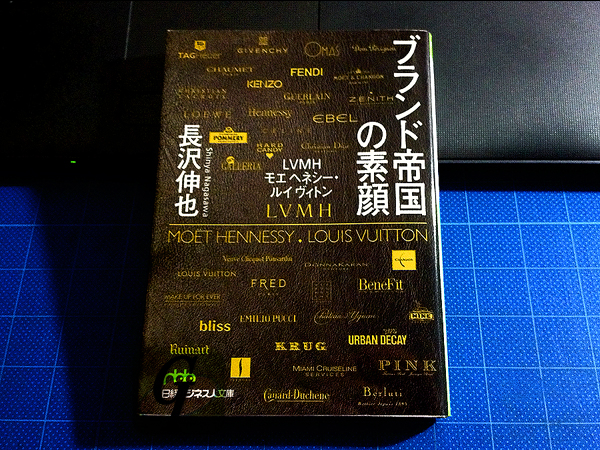
一概にライセンスを切ることを決断して実行できるかと言えば、アタマでは分かっていてもかなり難しい。実際に企業を経営していくなかで大変な困難に直面する。
仮に、部分的ライセンスに手を染めた場合でも同様である。品質と価格決定のコントロールを失いかねないからだ。
ライセンスを一切やめるとしても、巨額なロイヤリティー収入が途絶え、ライセンスを収益の柱としていた場合、企業を維持できなくなる。
LVMHの場合、ファインチューニングをしながら、ライセンスを切っていっている。
収入減を耐える事ができ、比較的ブランドを再生させる手法も持っているが、成長を得られないブランドもあり、その場合は事業売却なども行われている。
ライセンスを切り替え自前主義をするにしても。単独の中小ブランドでは、再生は難しい。
ライセンスを切り、ブランドが自前で運営する為の必要なサポート体制を充実させる事で、長期的なブランド・エクイティを最大限増大させることが出来ることも、資本力を生かしたLVMHの強みなのだろう。
参照書籍:ブランド帝国の素顔―LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン
 Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"
Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"